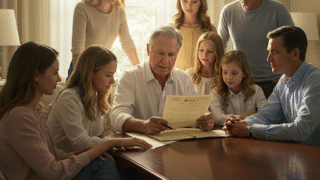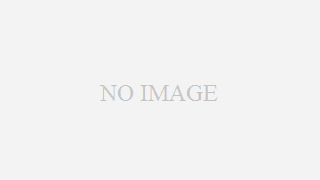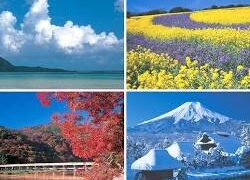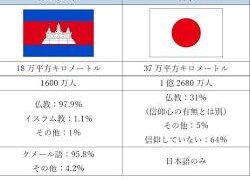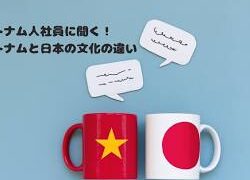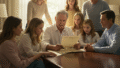遺言を残すために方法と種類を知っておこう
日本における遺言には、大きく分けて3つの種類があります。
遺言の種類
- 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごごん)
- 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
- 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
これらの他に、特別な状況下で作成される「
各遺言方法の詳細
1. 自筆証書遺言
- 作成方法:
- 遺言者自身が、遺言書の「全文」「日付」「氏名」を自筆で書き、
押印する必要があります。 - ただし、財産目録については、
2019年の民法改正によりパソコン等で作成したものでも認めら れるようになりました(ただし、 目録の全てのページに自筆での署名と押印が必要です)。 - 鉛筆ではなく、
消せないボールペンや万年筆で書くことが望ましいとされています 。
- 遺言者自身が、遺言書の「全文」「日付」「氏名」を自筆で書き、
- メリット:
- 費用がかからない。
- いつでも、どこでも手軽に作成できる。
- 遺言の内容を誰にも知られずに作成できる。
- 修正や書き直しが容易。
- デメリット:
- 方式に不備があると無効になるリスクが高い。
- 紛失、隠匿、改ざん、破棄される可能性がある。
- 遺言者の死後、家庭裁判所での「検認手続き」が必要となる(
ただし、法務局の「自筆証書遺言保管制度」 を利用した場合は不要)。 - 文字が書けない場合は作成できない。
- 注意点:
- 日付は特定できる形で記載する(「〇月吉日」などは無効)。
- 押印は実印が望ましい。
- 法務局の保管制度を利用すると、
紛失や改ざんのリスクを避けられ、 形式的なチェックも受けられるため、より安全性が高まります( 手数料3,900円)。
2. 公正証書遺言
- 作成方法:
- 遺言者と2人以上の証人が公証役場に出向き、
公証人の面前で遺言の内容を口述します。 - 公証人がその内容を筆記し、遺言者、証人、
公証人が内容を確認して署名・押印することで完成します。 - 病気などで字が書けない場合でも、公証人が代書できます。
- 遺言者と2人以上の証人が公証役場に出向き、
- メリット:
- 公証人が作成するため、
方式の不備による無効のおそれが極めて低い。 - 原本が公証役場に保管されるため、紛失、隠匿、改ざん、
破棄の心配がない。 - 相続発生後の家庭裁判所での「検認手続き」が不要なため、
すぐに遺言内容の実現に取りかかれる。 - 遺言能力についても公証人がチェックするため、
後で遺言能力が争われるリスクが低い。
- 公証人が作成するため、
- デメリット:
- 公証役場への手数料がかかる(遺産額によって変動)。
- 公証人や証人2人に遺言内容が知られる(ただし、
守秘義務がある)。 - 公証役場とのやり取りや、証人を探す手間がかかる。
- 注意点:
- 証人には、相続人やその配偶者、直系血族などはなれません。
3. 秘密証書遺言
- 作成方法:
- 遺言者が遺言書を作成し(自筆でなくても、
パソコンや代筆でも可)、署名・押印します。 - その遺言書を封筒に入れ、
遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印します。 - その封書を公証人と2人以上の証人の前に提出し、
自分の遺言書であることを告げ、住所氏名を述べます。 - 公証人が、封書に提出日と遺言者の申述内容を記載し、遺言者、
証人、公証人が署名・押印します。 - 封印された遺言書は、公証役場では保管されず、
遺言者が持ち帰って保管します。
- 遺言者が遺言書を作成し(自筆でなくても、
- メリット:
- 遺言の内容を誰にも知られずに作成できる。
- 全文自筆でなくても作成できる。
- 公正証書遺言よりも手数料が安い(一律11,000円)。
- デメリット:
- 公証人は遺言書の内容を確認しないため、
方式の不備で無効になるリスクがある。 - 遺言者が持ち帰って保管するため、紛失、隠匿、
破棄される可能性がある。 - 相続発生後の家庭裁判所での「検認手続き」が必要となる。
- 証人2人が必要。
- 公証人は遺言書の内容を確認しないため、
- 注意点:
- 内容に不備がないか、
弁護士などに事前に確認してもらうことが推奨されます。
- 内容に不備がないか、
遺言の法的有効性について
- 要件の厳格性: 遺言は、
民法で定められた厳格な方式に従って作成されなければ無効となり ます。形式的な要件を満たしていない場合、 たとえ遺言者の真意であっても法的な効力は認められません。 - 遺言能力: 遺言を作成するには、遺言者に「遺言能力」
があることが必要です。これは、 遺言の内容とその結果を理解して行動できる能力を指します。 認知症などで判断能力が低下している場合、 遺言が無効となる可能性があります。 - 法定遺言事項: 遺言で法的な効力を持つのは、「法定遺言事項」
と呼ばれるものに限られます。例えば、相続分の指定、 遺産分割方法の指定、遺贈、認知、 後見人の指定などがこれにあたります。これら以外の事柄(例: 家族への感謝の気持ちなど)は、 遺言書に記載しても法的な効力はありません。 - 複数の遺言: 複数の遺言書が存在する場合、内容が抵触する部分については、
最も新しい日付の遺言書が優先されます。ただし、 抵触しない部分は、古い遺言書も有効である場合があります。 - 遺留分: 遺言によっても、一定の相続人(兄弟姉妹以外の法定相続人)
には「遺留分」 という最低限の相続財産を受け取る権利が保証されています。 遺言で遺留分を侵害する内容が書かれていても、 遺留分権利者は侵害額請求をすることができます。
どの遺言方法を選ぶかは、費用、手間、秘密性、
|
返信転送
|